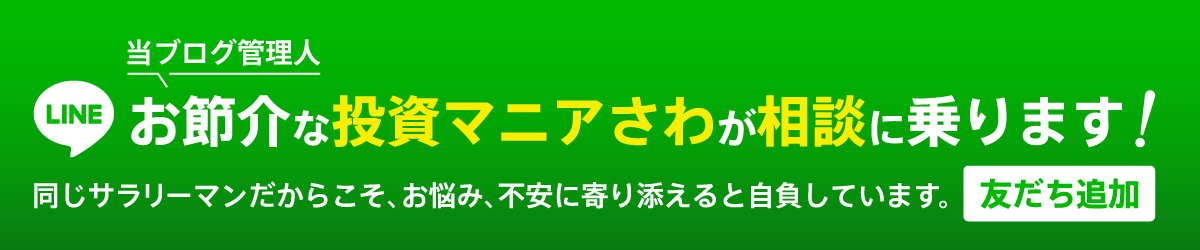年収1900万円の節税・税金対策とは?一般的な方法から不動産投資を活用して節税金額を最大化する手段まで!

こんにちは!
投資マニアさわです。
◆限界まで節税したい
◆投資で成功したい
◆優良な投資先の見つけ方が知りたい
◆投資先の利回りの改善
◆不労所得を作りたい
◆投資先を解約、資金回収したい
当てはまる方は私にお任せください!
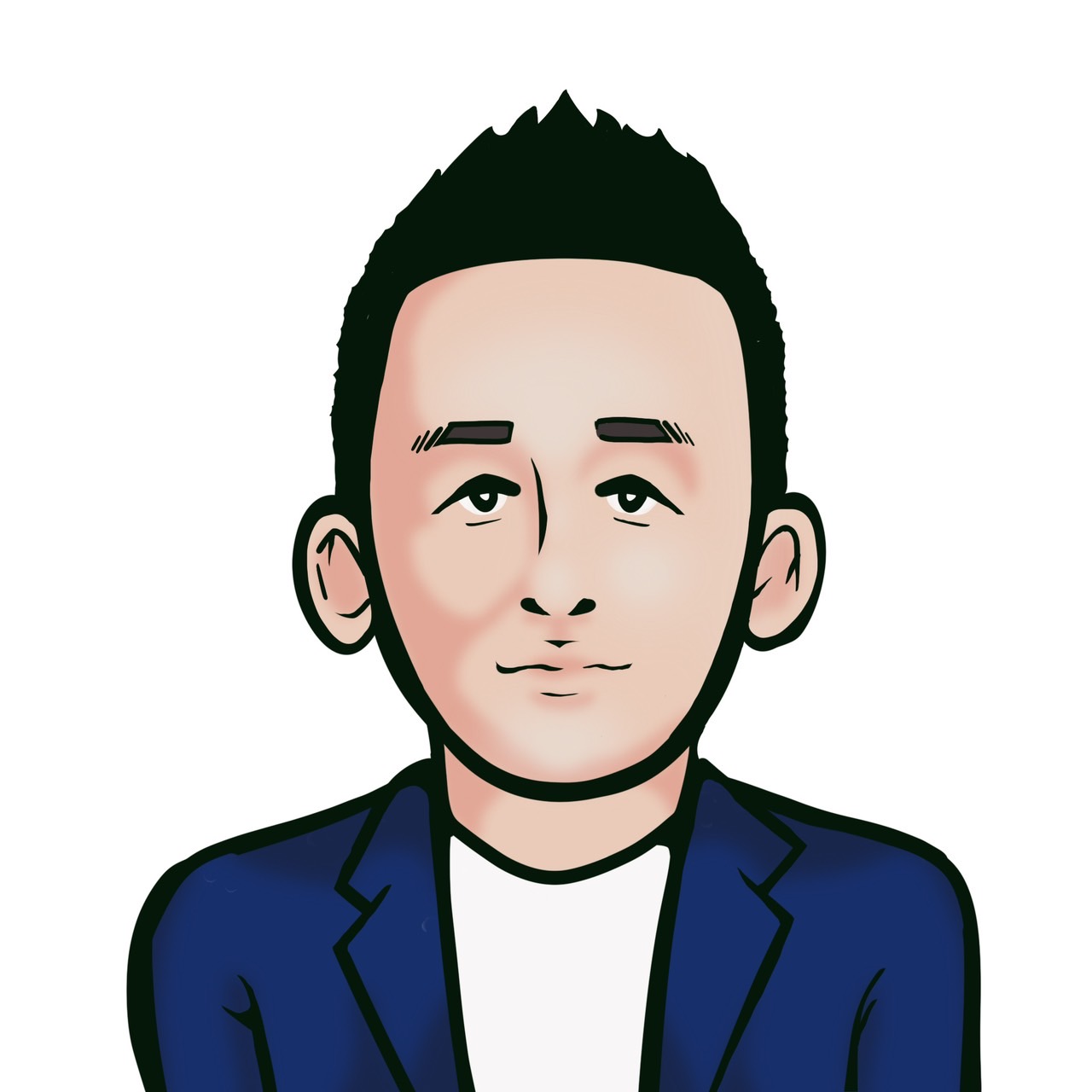
41歳の投資マニアです。ほったらかしでお金が増える投資が大好物。不動産投資を基盤としています。現在、約30種類の投資を実践し、投資運用総額約6億円。年間手取り家賃収入約800万円。現在IT系コンサルティング企業勤務。過去には金融機関や外資系IT企業に勤務。宮崎県出身。1児の父。
年収1900万円の人は税金が高く、収入から多額のお金が引かれてしまうので、節税を考える人は多いでしょう。
そこで本記事では、一般的に活用されている節税方法や、状況に応じておこなえる節税方法を合わせて8つ解説します。
年収1900万円の場合、税負担をどう減らすかが重要な課題
年収1900万円の人は税負担が大きく、どのようにして減らすかが資産形成において重要な課題です。
累進課税により収入の33%が税金として徴収される
年収1900万円の人は累進課税制度が適用されるため、課税所得の33%が税金として徴収されます。
累進課税制度とは、以下のように所得や財産などが多いほど税金が高くなっていく仕組みです。
年収1900万円の人の課税所得は世帯構成にもよりますが、およそ1300万~1500万円くらいが目安となり、以下を見ていただくと33%の税率が適用されることがわかります。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000円 から 1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
さらに収入にかかわらず一律で納める住民税の10%を含めれば43%と、年収の半分近くが税金で徴収されてしまいます。
頑張って稼いでも税金として消え、生活費や貯蓄に回せる額が減るのを避けるためには、節税が必須です。
生活レベルが上がるぶん老後の不安も大きくなる
年収1900万円の人は生活レベルが上がる一方で、老後の不安も大きくなる傾向にあります。
なぜなら、収入に対して手元に残るお金がそこまで多くないからです。
年収1900万円の人の手取りは世帯構成によりますが、ひと月約100万円、年間約1200万円ほどです。1か月に100万円以上使えるのならしっかり貯蓄できるように感じられますが、実際は生活費や教育費、交際費などがかさみ、手元に残るお金はそこまで多くありません。
年収1900万円の人の住宅ローン目安は9500万~1億1400万円となり、タワーマンションや高級住宅地の持ち家などに、毎月約35万ほどの住宅費をかけるケースが一般的です。
外食や子どもの教育費へかけるお金もかさむ傾向にあり、私立の学校へ通うとなれば塾の費用や交通費も発生します。さらに旅行や高級品の購入といった贅沢費による支出も増えやすく、結果的に手元にほとんどお金が残らない状況へと陥りやすくなります。
計画立てて貯蓄をしていかなければ老後に生活レベルを落とさざるを得ないため、年収が1900万円あったとしても、税負担を抑えていく必要性は高いです。
年収1900万円の人ができる一般的な節税方法6つ
ここまでで年収1900万円の人にとって、節税が欠かせないことをおわかりいただけたでしょう。
では実際どのように節税していけばいいのか、年収1900万円の人ができる一般的な対策を見ていきましょう。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、厚生年金や国民年金などの公的年金とは別に受けられる、私的年金制度です。
20歳以上65歳未満の公的年金の被保険者がiDeCoへ加入でき、自分で設定した掛金を積み立てながら運用し、60歳以降から受給できる仕組みです。
iDeCoの節税メリットは、タイミングに応じて以下の3つがあります。
| タイミング | 節税メリット |
| 積立時 | 掛金が全額所得控除 |
| 運用時 | 運用利益が非課税 |
| 受取時 | 受取り方法を問わず、一定額まで非課税 |
まずiDeCoの積立時は掛金が全額所得控除となり、所得税と住民税が毎年軽減されます。
投資信託のような金融商品では、利益が出ると通常20.315%の税金がかかってしまうものの、iDeCoではすべて非課税となり有利にお金を増やせます。さらに60歳以上になり受け取るときには一括、もしくは分割といった受取り方法ができますが、どの受給の仕方でも税金が発生しません。
たとえば年収1900万円の人が毎月20,000円を35~65歳まで積み立てたと仮定すると、以下のように30年で3,096,000円の節税効果を見込めます。
| 軽減される税金 | 1年の軽減額 | 30年の軽減額 |
| 所得税 | 79,200円 | 2,376,000円 |
| 住民税 | 24,000円 | 720,000円 |
ただし、掛金の上限が月額2万3000円と制約があるため、節税効果には限界があります。また、資金を60歳まで引き出せないため、流動性を考慮する必要もあります。
とはいえ、長期的にみれば節税効果が見込めるため、活用しない手はありません。
ふるさと納税
ふるさと納税は自分の故郷や応援したい地域など、任意の自治体へ寄付できる制度です。寄付した金額から2,000円を引いた全額が確定申告により所得控除されるので、ふるさと納税を活用すると所得税や住民税を節税できます。
年収1900万円の人がふるさと納税をする場合は、世帯構成によって変動するものの、実質負担2,000円で、500,000~533,000円の所得税・住民税が控除されます。
またふるさと納税をすると税額控除されるだけでなく、寄付した自治体から名産品や宿泊券などの返礼品をもらえるので、メリットは大きいでしょう。
ただし注意点として、ふるさと納税も控除の上限額が決められているので、寄付すればするほど節税になるわけではありません。
控除の上限額を超えてしまえば自己負担となり、節税のメリットは得られなくなります。
ふるさと納税を活用する場合は、寄付金を受け付けているサイトや以下の総務省の表を参考に、自身の控除額を把握したうえで寄付しましょう。
>総務省「全額(※)控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安 (※) 2,000円を除く」
生命保険料控除
生命保険を支払っている場合は確定申告により生命保険料控除を受けられ、節税につながります。
契約した時期に応じて生命保険料控除には新制度と旧制度があり、2011年以前の契約であれば合計適用限度額は所得税10万円、住民税7万円までですが、2012年からは引き上げられて所得税12万円、住民税7万円となっています。
仮に年収1900万円の人が2012年以降に生命保険を契約しており、上限まで控除を受けたら、46,600円節税できます。
| 年収1900万円、所得税率33%、住民税10%の場合 | |
| 所得税の軽減額 | 39,600円 |
| 住民税の軽減額 | 7,000円 |
| 合計の節税効果 | 46,600円 |
ただし、生命保険控除を受けるには対象の生命保険と契約していなければなりません。
一般的な生命保険の多くは生命保険控除の対象ですが、以下のような保険は対象外となります。一応把握しておきましょう。
| 生命保険控除の対象外となる保険 |
|
出典:国税庁「No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等」
NISA(少額投資非課税制度)
NISA(少額投資非課税制度)は投資の運用益にかかる20.315%の税金が非課税になる制度です。
2025年現在のNISAは2024年1月から制度が変わり、以下の内容となりました。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
| 対象年齢 | 18歳以上 | |
| 運用期間 | 無期限 | |
| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
| 非課税保有限度枠 | 1,800万円 | |
| 対象商品 | 積立、分散投資に適した銘柄 (金融庁の基準を満たす投資信託) |
株式・投資信託など |
参考:金融庁「NISAを知る」
2024年1月から始まったNISAにはつみたて投資枠と成長枠があり、年間の投資枠や対象商品が異なりますが、併用しながら運用できます。
仮に毎月3万円、利回り3%で20年間運用すれば将来の運用資産は約985万円を見込め、非課税による税金の軽減効果は55万円弱です。
NISAで積み立てていなければ課税されて55万円弱が税金として引かれ、受け取るときに少なくなってしまいます。
投資をしながら資産を増やすのであれば、NISAの活用が有効な手段のひとつです。
医療費控除
医療費控除は1月1日~12月31日までの1年間で、医療費が10万円を超えたら最大200万円まで所得控除を受けられる制度です。
医療費の計算には自身だけでなく生計を共にする家族も含めることができ、確定申告することで所得控除を受けられます。
| (医療費総額ー補填金額(保険金や医療証など))-10万円=医療費控除額 |
たとえば以下のようなケースでは、11万円の医療費控除を受けられます。
| 年間の医療費:夫20万円、妻3万円、子ども1万円
保険で返ってきた医療費:3万円 (20万円+3万円+1万円ー3万円)ー10万円=11万円 |
年収1900万円の人は所得税率33%なので、以下のように36,300円の所得税が還付される計算になります。
| 11万円×33%=36,300円 |
ただし、病院への受診すべてが医療費控除の対象になるわけではありません。
美容整形費やビタミン剤といった費用は認められないので注意が必要です。
以下のように医療費控除が適用されるケースは幅広いですが、対象外の場合もあるのであらかじめ国税庁の「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」を確認しましょう。
| 医療費控除の対象 |
|
参考:国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」
住宅ローン控除
住宅ローンを利用してマンションや戸建ての購入をすると、確定申告により住宅ローン控除を受けられ節税できます。
2022年度の税制改正により、2025年3月現在では年末時点の住宅ローン残高の0.7%が、所得税・住民税から最大13年にわたって控除されます。
| 住宅の種類 | 住宅の性能 | 借入限度額 | 控除期間 | |
| 令和6年入居 | 令和7年入居 | |||
| 新築 買取再販 |
|
子育て世帯・若者夫婦世帯:5,000万円 その他の世帯:4,500万円 |
4,500万円 | 13年間 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 子育て世帯・若者夫婦世帯:4,500万円 その他の世帯:3,500万円 |
3,500万円 | ||
| 省エネ基準適合住宅 | 子育て世帯・若者夫婦世帯:4,000万円 その他の世帯:3,000万円 |
3,000万円 | ||
| その他の住宅 | 0円 | – | ||
| 既存住宅 |
|
3,000万円 | 10年間 | |
| その他の住宅 | 2,000万円 | |||
住宅ローン控除額は「年末の住宅ローン残高×0.7%」で計算するので、年末のローン残高が4,000万円のケースでは、以下のように28万円還付となります。
| 年末のローン残高4,000万円のときの住宅ローン控除額
4,000万円×0.7%=28万円 |
このとき28万円すべてが還付されるかは「借入限度額」と「年収」に左右されますが、年収1900万円の人であれば28万円満額の控除を受けられる可能性が高いでしょう。
実際にいくら節税できるかは、金利や入居年月などさまざまな要件によって左右されるので、各サイトのシミュレーションなども参考にしてみてください。
年収1900万円の人の節税には不動産投資がほぼ唯一の解
ここまでさまざまな節税方法をお伝えしてきましたが、いずれも節税効果は限定的であり、年収1900万円の人が本格的に節税するなら不動産投資が最適です。
ここでは年収1900万円の人の節税になぜ不動産投資が適しているのか、具体的な理由を見ていきましょう。
減価償却を活用した長期的な節税効果を得られる
不動産投資では減価償却を活用できるので、毎年購入費用を少しずつ経費計上しながら長期的な節税効果を得られます。
| 減価償却:固定資産を購入したときに一度で経費とせず、耐用年数に分割して計上すること |
たとえば2,000万円のマンションを購入し、耐用年数が20年だったと仮定しましょう。
不動産などの購入価格の大きなものは、購入年で2,000万円を一度に経費計上するのではなく、以下のように耐用年数で分割して経費として計上します。
| 2,000万円÷20年=100万円 |
※実際はもう少し複雑な計算式となりますが、今回はわかりやすく単純化しています。
そのため年収1900万円の人が仮に課税所得1,400万円だった場合、減価償却により100万円を経費として引くと、以下のように33万円の節税となります。
| 課税所得1,400万円の所得税:1,400万円×33%=462万円
課税所得1,300万円の所得税:1,300万円×33%=429万円 462万円-429万円=33万円 |
※課税所得9,000,000円 から 17,999,000円までの税率33%
このように不動産投資なら耐用年数まで毎年大きな金額を経費として申告できるので、長期的に節税効果を得られます。
国や公共団体の福利厚生を享受しやすくなるメリットも
節税効果は不動産投資の大きな魅力のひとつですが、メリットはそれだけではありません。帳簿上の赤字を増やすことで「見かけ上の年収」を引き下げることができます。
例えば年収1,900万円の人が、不動産投資により400万円の赤字を出せば、課税所得を1,500万円に抑えることが可能です。投資の規模を拡大すれば、年収を800万円程度に“見せる”こともできるでしょう。
このようにして年収が一定の基準を下回ると、自治体によっては育児手当や高校授業料の無償化、不妊治療の助成金など、各種の行政サービスや福祉制度の対象になりやすくなるという副次的なメリットも生まれます。
単なる節税にとどまらず、実生活に直結する恩恵を受けられる可能性があるのも、不動産投資の見逃せないポイントです。
高額融資を受けられる可能性が高く、ローンの選択肢が多い
年収1900万円の人は高額融資を受けられる可能性が高く、ローンの選択肢が多くなります。
年収が低い人と比べて、年収1900万円の人は高収入で返済能力が高いと見なされるからです。返済能力が高ければ高額な融資でも金融機関は積極的になり、低い金利や自己資金無しなど幅広い選択肢のローンを提示してくれます。
融資面で優遇され、良い条件でローンを組めるのは高収入の人ならではの不動産投資における大きな強みです。
老後を支える資産を形成できる
不動産投資は、以下の理由から老後を支える資産形成に適しています。
- 長期的な安定収入を得られる
- 不労所得を得られる
入居者が何年も同じ物件に住むことは珍しくなく、一度決まれば安定した収入を毎月得られます。実際に、日本賃貸住宅管理協会の調査では、2021年度の入居者平均居住期間(全国)は4年1か月でした。(出典:公益財団法人日本賃貸住宅管理協会「第26回 賃貸住宅市場景況感調査『日管協短観』」)
特に、高所得者がターゲットとする都市部のRC物件は、資産価値の下落が少なく、数十年後も収益をもたらします。将来の経済的な安心を得るためには、現役時代の高収入を活かして早めに資産形成を開始することが重要です。不動産は、適切に管理すれば世代を超えて資産を引き継ぐことも可能です。
手出しがほぼなく現在の生活に影響が少ない
不動産投資はローンを使って投資ができるので、株式や債券などの投資とは違い手出しがほぼなく、現在の生活に影響が少ない点もメリットです。
仮に6000万円の不動産を購入したとしても、初期費用は数百万円程度で済みます。
また、家賃収入がローン返済額を上回れば、現金収支がプラスになるため、手元資金を削らずに資産形成が可能です。年収1900万円の方であれば、無理なく運用を開始でき、現行の生活水準を維持しながら将来の備えを進められるのが魅力です。
年収1900万円の人が不動産投資に取り組む際の注意点
最後に、年収1900万円の人が不動産投資に取り組む際の注意点を3つお伝えします。
節税だけを目的にしない
不動産投資をするにあたって、減価償却費の大きさを重視した節税だけを目的にして始めるのはやめましょう。目先の減価償却費だけを見て不動産投資をすれば、減価償却が終わったあとに節税効果がなくなり、かえって税負担が増加するリスクが高まるからです。
たとえば築古木造物件は耐用年数が4年と短く、大きな減価償却費を魅力として営業されるケースも少なくありません。
先ほどの例でいうと、2000万円で築古木造一棟アパートなどを買った場合、耐用年数は4年ですから、1年あたり500万円が経費計上できることになります。しかし減価償却を終えた5年後からは、帳簿上の利益が所得に上乗せされて課税されます。
実際のキャッシュフローは引き続きローンを返済している状況ですから、上乗せされた税負担を給料から支払うことになります。
さらに築古木造物件はリセールバリューが低いことも多く、売り手がつかない可能性も懸念されます。売却できなければ重い税負担がのしかかり続けることとなるため、結果的に減価償却中に得られた節税効果以上に損をする可能性が高いのです。
そのため、不動産投資をする場合は節税額の大きさだけでなく将来的な資産価値や、出口戦略を十分に考慮する必要があります。
資産価値が下がりにくく減価償却期間の長い物件を重視し、都市部のRC物件や区分マンションなどを検討しましょう。
空室リスクを過小評価しない
不動産投資では、所有物件に入居者が決まらず家賃収入がゼロになる「空室リスク」を過小評価してはいけません。
不動産購入時の初期費用を減価償却して節税できても、利益が出なければ返済計画に影響が生じて物件を手放すことになります。
また空室が続けば資産価値の低下を招く恐れもあるため、以下を参考にしながら慎重に物件を選んだうえで投資しましょう。
| 物件を選ぶポイント | 概要 |
| 賃貸需要の安定したエリアを選ぶ |
|
| 立地の良い物件に投資する |
|
| 入居者目線で魅力的な物件に投資する |
|
高所得者をカモにする業者に注意する
不動産投資をするとき、高所得者をカモにする業者がいる点にも注意してください。
高所得者は、以下2つの理由から業者から狙われることがあります。
- ローンの審査が通りやすい
- 本業が忙しく不動産に関する知識がない
高収入がゆえに高所得者はローン審査に通りやすい傾向にあり、業者にしてみるとその気にさせれば物件の購入にこぎ着けられるいいカモです。「必ず儲かる」「高利回りで運用できる」などの謳い文句をかけられ、利益にならない不動産を業者から売りつけられるケースがあります。
業者の言葉を鵜呑みにするのではなく、投資家自身でも不動産投資について勉強しながら、新しい知識や情報を常日頃からインプットしましょう。
まとめ
本記事では年収1,900万円の人になぜ節税が重要なのか、どのように節税していけばいいのかについて解説しました。年収1,900万円の人は支払う税金が多く、生活レベルも上がるため資産形成をしていかなければ老後に不安を抱えることとなります。
そこで重要になるのが高額な所得を抑える節税であり、さまざまな方法をお伝えしたなかでもっともおすすめなのが不動産投資です。節税になるだけでなく、手出しの少なさや融資の受けやすさなど数多くのメリットがある不動産投資は、年収1900万円の高所得者の人にとって最適な節税方法といえるでしょう。
ただし節税目的だけで不動産投資をしたり、勉強せずに手を出せば業者のカモにされたり、注意点もあります。不動産投資はあくまでも投資なので、知識や情報を身につけたうえで始めましょう。
投資の詳細はプロフィールに書いてあります!